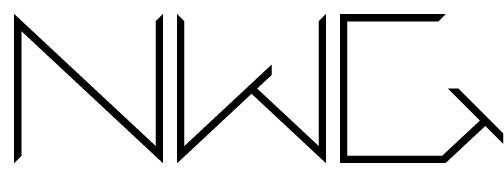循環器内科の医師である宮脇 大氏は、多くの生活習慣病・心疾患の患者を治療するなかで、運動療法の大切さを感じ、運動施設を併設した診療所を立ち上げました。さらに、積極的に周囲のフィットネス施設とも連携し「メディカルフィットネス」を増やそうと取り組んでいます。宮脇氏に、医療機関とフィットネス施設が連携するために重要なポイントについてお聞きしました。
INDEX
PROFILE
宮脇 大 株式会社Doctor’sFitness 代表
2011年、大阪大学医学部医学科卒業。2022年に株式会社Doctor’sFitnessを立ち上げ、病気の治療だけに留まらず、予防医療や健康寿命の延伸にも力をいれる。2024年からは運動指導者が医療分野の知識を学べる「Doctor’s Fitness Academy」もスタートした。趣味ではクロスフィットに取り組んでおり、CrossFit Level 1 トレーナー・CrossFit認定医師としても活動している。
1. 健康増進のために診療所にスタジオを併設——「運動しましょう」から「ここで運動できます」へ
私は循環器内科の医師として、これまで心臓病や高血圧、動脈硬化、不整脈などの患者さまを多く診てきました。これらは「生活習慣病」と言われるように、肥満や身体活動不足など生活習慣に原因がある方も多く、そのような方には「運動しましょう」とお伝えしますが、その言葉だけで実際に行動を起こす方はごくわずかです。
一方、医療機関の心臓リハビリテーション施設には真剣に運動に取り組んでいる方がいますが、保険が適用されるのは最大150日間。それ以降は患者さま自らフィットネス施設を探さなければなりません。これらの課題を解決するため、大阪で株式会社Doctor’s Fitness(以下、ドクターズフィットネス)を立ち上げ、「ドクターズフィットネス診療所」および、診療所に併設する形で「ドクターズフィットネススタジオ」をオープンしました。ここでは、生活習慣病の治療に加え、栄養・睡眠・運動など、健康に関するトータルサポートを提供しています。
「ドクターズフィットネススタジオ」では、国立循環器病研究センターの心臓リハビリテーションと同一のプログラム「運動療法体操」を毎週実施しています。このプログラムは、ご高齢の方や身体に疾患をお持ちの方など、どなたにも「私でもできる」と感じていただけるよう、常に同じ内容で提供しています。
さらに、毎週同じ曜日・同じメンバーで行うことで、習慣化やコミュニティ形成につなげています。 その結果、参加者の95%以上の方が1年以上継続し、血圧や血糖値が改善した例も多く報告されています。2~3ヶ月ごとに私自身が講師となり、インフルエンザ対策や腸活など、その時々に応じた勉強会も開催し、健康に関する知識も高められるよう取り組んでいます。

2. より幅広い層の健康を支える「メディカルフィットネス」
フィットネス業界の方なら「メディカルフィットネス」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。厳密な定義はありませんが、医療機関と良好なパートナーシップを構築しているフィットネス施設と捉えてよいでしょう。ドクターズフィットネスも複数のフィットネス施設と連携し、私自身が医師として会員さまへの運動指導についてアドバイスを提供するなど、「メディカルフィットネス」の運営を支援しています。
医療機関と連携することで、一般的なフィットネス施設と比較して「メディカルフィットネス」はより幅広いお客さまを受け入れることができます。「メディカルフィットネス」にすることで会員数が急増するわけではありませんが、ドクターズフィットネスと提携した施設からは、以下のような声が寄せられています。
「毎月1~2名、新規入会者が増えた」
「健康を意識し始めた中高年層の入会が増加」
「医療機関からの紹介で来る方が増えた」
なにより、より多くの方の健康に貢献できることが、フィットネス業界で働く方々のモチベーションの向上につながっているようです。
3. 運動指導者が医療知識を学ぶアカデミーを設立し、共通言語を生み出す
「メディカルフィットネス」という言葉自体は数十年前から存在していますが、実際に普及しているとは言えません。私が考える、その要因と解決策を以下に挙げましょう。
3-1. 運動指導者に医療知識が不足している
「メディカルフィットネス」が広がらない最大の要因として、医療業界では、運動指導者の「病気や健康に関する医療的知識」が、運動療法を依頼する「医師」が求めるレベルに十分に達していないことが指摘されています。例えば、トレーナーがお客さまから「最近、血糖値が上がったから運動するように医師に言われました」と相談されたとき、「では、もっと運動を頑張りましょう!」と言うだけでは不十分です。「血糖値はどれくらいですか?」「ヘモグロビンA1cの値は?」と踏み込んだ質問ができ、適切な改善策を提案できるトレーナーがいる施設であれば、医療機関も安心して患者さまを紹介できます。
しかし、運動指導者が医療知識を学ぶ機会は限られています。そこで私は「ドクターズフィットネスアカデミー」を設立しました。医師として運動指導者に身に付けて欲しい「医療」や「医学」の知識を提供し、フィットネス施設と医療機関が共通言語でコミュニケーションできる環境を目指しています。 すでに「より多くの方を健康にしたい」という想いをもつ多くのインストラクターやパーソナルトレーナーの方が「ドクターズフィットネスアカデミー」に参加しています。

3-2. 医療連携が形骸化している
「メディカルフィットネス」の中には、医療機関との連携が形骸化してしまっている施設もあるようです。「メディカルフィットネス」として期待されたサービスを提供できなければお客さまの信頼を失い、施設に対してネガティブな印象を与えてしまいます。
医療機関とフィットネス施設がしっかりと信頼関係を築き、連携していくためには、時間と場所を共有し、定期的な情報共有を行うことが欠かせません。この関係性における重要なキーワードとして、私は「Coexistence=時間と場所を共有する」を提唱しています。
3-3. 医療機関側にフィットネス施設と連携する必要性が低い
医師は日ごろから看護師や管理栄養士、理学療法士などと連携してサービスを提供しています。「連携」することには慣れていますが、外部組織との連携・民間フィットネス施設との連携に経験値が低いのが実情です。しかし、「人を健康にしたい」という想いは医師も同じはずですから、医師側に連携のメリットを適切に伝えることが重要になります。その際、私のような同じ「医師」という立場から相談する方が、賛同を得られやすいかもしれません。実際、私が仲介役となり、フィットネス施設と医療機関の連携が成功したケースもあります。
4. 医療面からのサポートを通じ、フィットネス施設とフィットネス自体の価値を高めたい
ドクターズフィットネスと国立循環器病研究センターとの連携が、心臓リハビリテーション学会で取り上げられたり、大阪府茨木市の特定保健指導(運動療法)に関する連携協定締結、大阪府スマートヘルスプロジェクトのアドバイザー就任など、私の取り組みが、行政機関からも非常に関心が集まっていることを実感します。今後も、フィットネス施設と医療機関との連携を広く発信していきます。
ドクターズフィットネスの立ち上げから約3年が経ち、少しづつ当社と連携するフィットネス施設が増え、全国から「ドクターズフィットネスアカデミー」への受講者が集まるなど同志も増えつつあります。また、医師、特に開業医の先生からの問い合わせも増えてきており、「メディカルフィットネス」への期待の高まりを実感します。仲間の輪が広がることで、健康になる方が増えるという好循環がうまくまわり出しています。今後もフィットネス施設を医療面からサポートすることで、フィットネス施設およびフィットネス自体の価値向上に努めていきます。