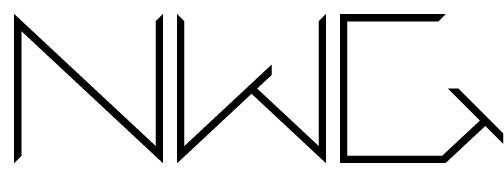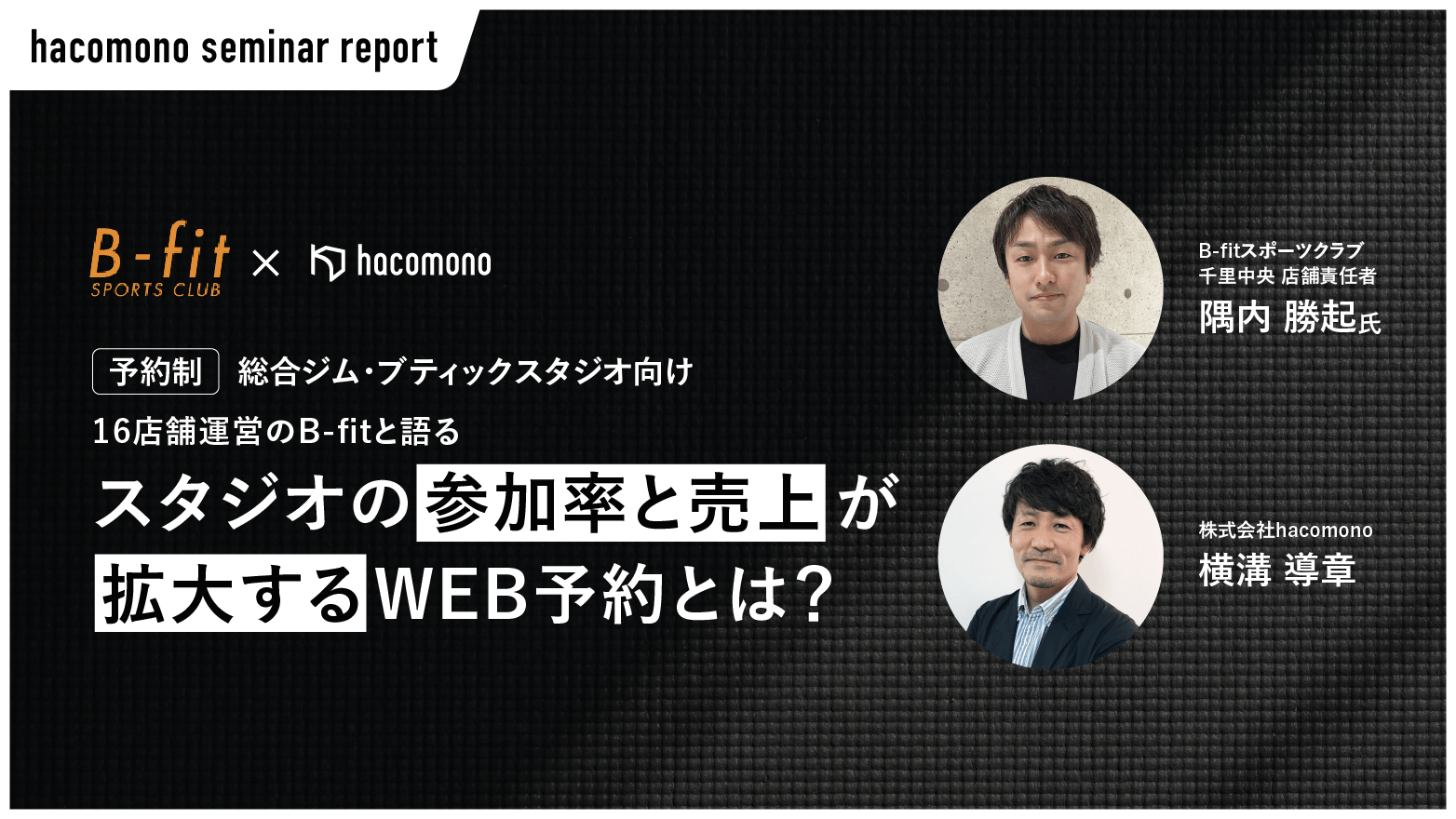「学びは、面白い。」をブランドスローガンに掲げ、あらゆる世代に向けて生涯教育を提供しているヒューマンアカデミー株式会社。同社は1985年に教育事業をスタートさせ、2009年からは子ども向けの教育コンテンツとしてロボット教室を開講。現在のヒューマンアカデミージュニアの礎となり、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(教養/創造性)、Mathematics(数学)を統合的に学ぶ「STEAM教育」を推進しています。ヒューマンアカデミージュニアは「 ロボット教室」をはじめ「こどもプログラミング教室」「科学教室」「さんすう数学教室」などを通じて、子どもの創造力と論理的思考力を育むことに取り組んでいます。同社 児童教育事業部の須藤冬暁氏、北川祐作氏、藤本美枝子氏に、教育への想いやSTEAM教育の可能性についてお話を伺いました。
INDEX
PROFILE
ヒューマンアカデミー株式会社
1985年、取締役ファウンダーである佐藤耕一氏が教育事業を目的として設立した「株式会社教育未来社」が起点となり、教育、人材・介護・保育・IT・美容・スポーツと多様な事業を展開する現在のヒューマングループを作り上げる。ヒューマンアカデミー株式会社は、その中心となる教育事業を担い、子どもから大人まで幅広い年齢層に向けて、様々なコンテンツを通じた学びの場を提供している。
1. STEAM教育との出会い、子どもへのアプローチで保護者の興味を喚起
—— ヒューマンアカデミージュニアを立ち上げた背景を教えてください。
もともと当社では、社会人教育や専門学校事業が大きな柱でした。しかし「学びは全年齢に等しくあるべき」という理念のもと、2009年に幼児教育事業をスタートしました。当時は「子どもの理科離れ」が社会問題として注目されており、ロボットクリエイターの高橋智隆先生とのご縁をきっかけに、理科への関心を高める「ロボット教室」を始めました。
—— 保護者の反応はどのようなものでしたか。
「ロボット=遊び」というイメージが強く、保護者やフランチャイズパートナーの理解を得るのに苦労しました。最初はポスティングなどを中心に保護者へ訴求していたのですが、なかなか成果が出ず…。突破口となったのは、学校前で子どもたちにチラシを配布したことでした。
—— 子ども本人に直接アプローチしたのですね。
プロモーションを「子ども目線」に切り替え、子どもから「行きたい!」「やりたい!」と言ってもらう流れをつくったことで、ようやく保護者の関心も高まりました。保護者には「子どもの得意を伸ばしたい」「好きなことを見つけてあげたい」という思いが強くありますから。

写真左より、須藤冬暁氏、藤本美枝子氏、北川祐作氏
2. 子どもが自ら学ぶ力を引き出すSTEAM教育のカリキュラムとは
—— 2017年には「こどもプログラミング教室」もスタートされました。
「理科好きの子を増やし、日本の科学立国に貢献したい」という理念のもと、子どもがワクワクしながら学び、自ら考えて創造する力を育むSTEAM教育に取り組んできました。今の子どもたちは2040年代の社会を支える存在。その未来に必要なのは、自らの頭で考え、テクノロジーを活用してイノベーションを起こせる人材です。
—— 少子化の中でも生徒数を伸ばすためには何が大切でしょうか。
何より大切にしているのは「子ども目線」です。学びそのものが“楽しい”と感じられる体験を提供しています。また、費用を負担する保護者への信頼感も重要ですので、子どもと保護者双方に価値あるカリキュラム設計と情報発信を心がけています。
—— 実際、保護者からの反応はいかがでしょうか。
「ロボット教室に通ってから、自分から進んで学ぶようになった」「積極的に発言するようになった」などのお声を多くいただいています。体験教室のたった1回で、子どもの顔つきが変わるのを実感される保護者も少なくありません。

3.成長の“見える化”で、継続につなげる運営体制を構築
—— 現在、どれくらいの子どもたちがSTEAM教育を受けていますか。
現在は全国で約10万人の子どもたちが受講していると見ています。ただ、習い事市場の全体から見るとまだ2%程度と、STEAM教育の普及はこれからが本番です。
—— STEAM教育の適齢期は何歳ぐらいなのでしょうか。
もっとも成長が著しいのは、年長〜小学校低学年の2〜3年間です。この時期に学びの“きっかけ”を与えることが、将来の選択肢を大きく広げます。体験教室では、子どもたちにとって“未来の原点”となるような出会いを提供しています。子どもの興味は多種多様なので、子どもが「やってみたい」と思うならば、ロボット教室やプログラミング教室、科学教室など、入り口は様々あっていいと思います。
—— 今、特に注力している施策はありますか。
2つあります。1つは「学びの可視化」です。ロボット教室での取り組みを、スキルとして“見える化”するため、検定制度を整備しています。もう1つは「中学受験による離脱」への対応です。平均在籍年数が約3年である現状を変え、より長く通いたくなる環境づくりに力を入れています。
—— そのために取り組まれていることはありますか。
外部団体として「一般社団法人 未来創生STREAM教育総合研究所」を立ち上げ、「クリエイティブロボティクスコンテスト」「クリエイティブロボティクス検定」など競合他社を巻き込みながらSTEAM教育の普及拡大を目標に推進しています。学びの過程を可視化し、成果を実感できる場をつくっており、地域ごとのイベント開催も進めています。
4.すべての子どもたちにSTEAM教育の機会を。未来を築く教育ビジョン
—— 5年後・10年後を見据えた目標を教えてください。
STEAM教育のさらなる普及です。現在、弊社の教室は全国で約1,700市町村のうち約800にしか展開できていません。残る900市町村の子どもたちにも、質の高い教育機会を届けたいと考えています。今は10万人規模ですが、中長期的には100万人規模の市場に育てていきたいという思いで日々取り組んでいます。
—— 最後に、保護者の方々へメッセージをお願いします。
子どもの成長は本当にあっという間です。短い幼少期に、一度でもSTEAM教育を経験してもらいたいです。夢中になって学び、自分で考えて行動する経験は、将来の自己決定力につながります。それはきっと、人生の大きな財産になります。
また、私たちのサービスが、保護者の意識や教育への考え方を変えるきっかけになればと思います。「学校のテストがすべて」ではなく、「好きなことを突き詰めて生きていける社会」へ——STEAM教育が、その土台になることを信じています。