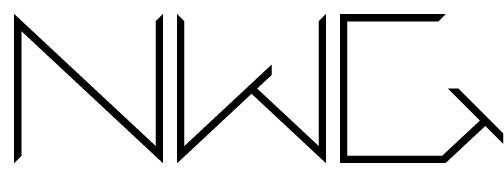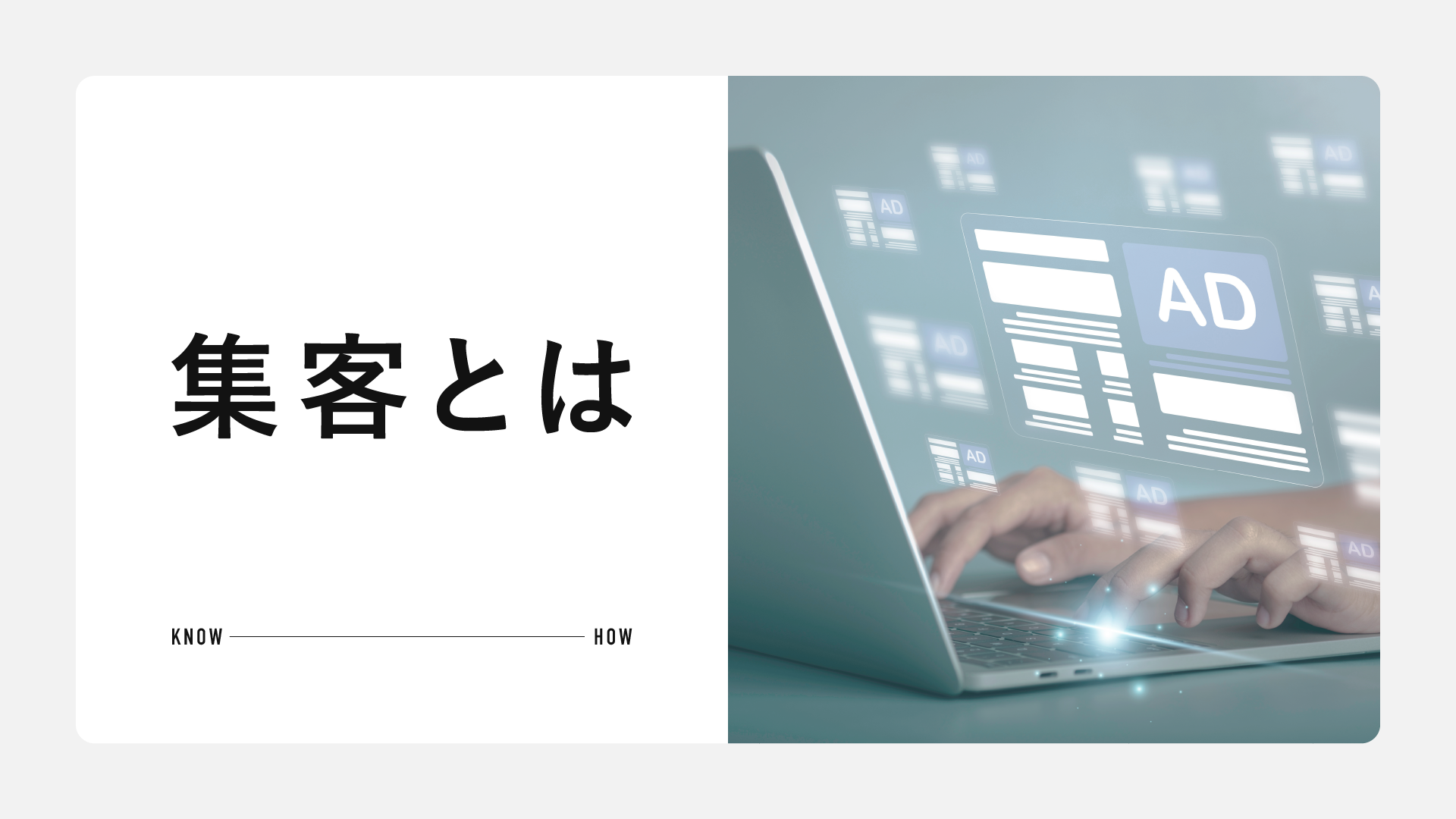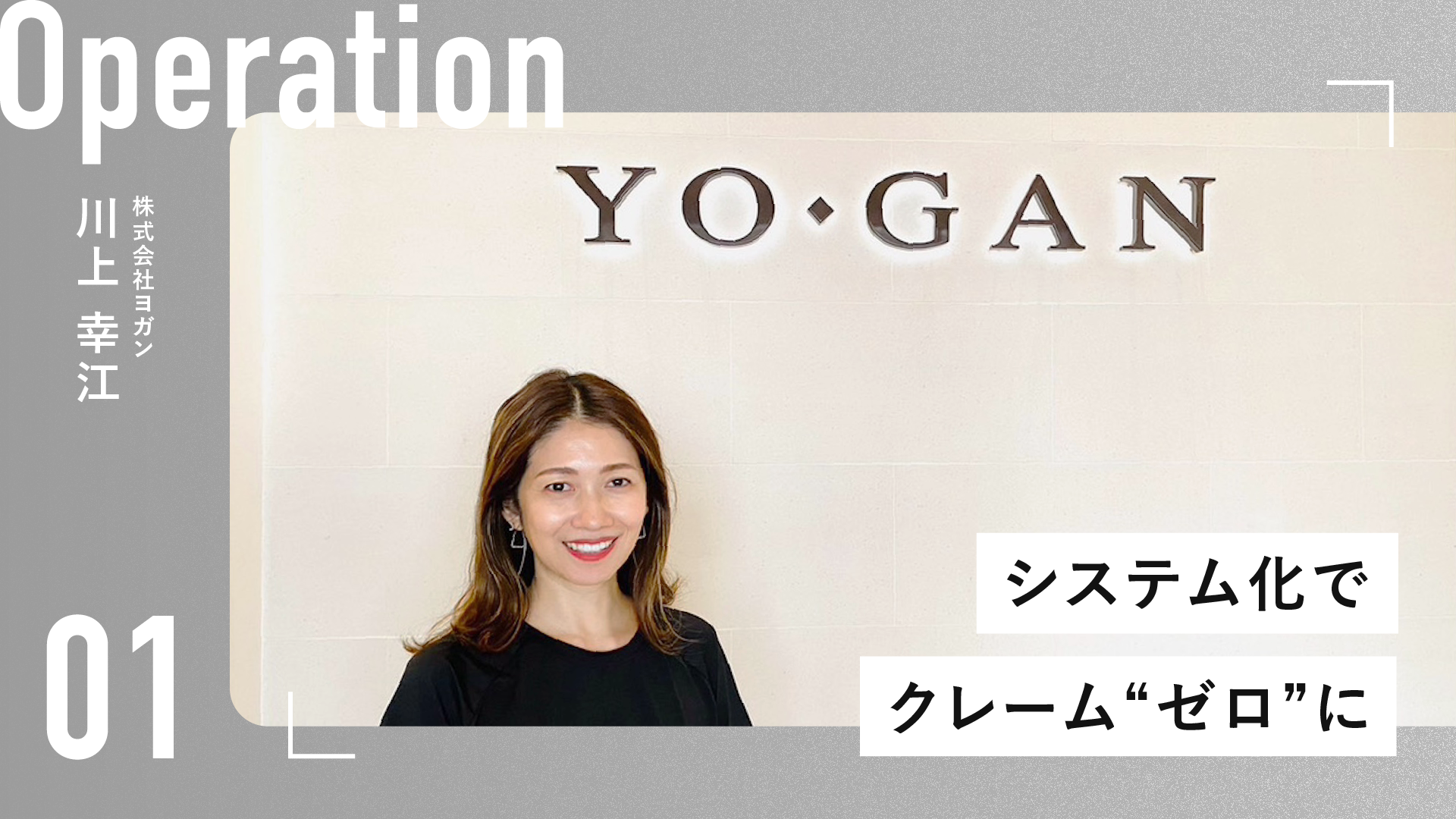顧客満足度向上と働き方改革を両立させるにはどうすればよいのでしょうか。1978年の創業以来、地域に愛され続けてきた山口県の周南スイミングクラブも、少子化とコロナ禍という大きな壁に直面しました。しかし同社は、単なる値上げやサービス削減ではなく、「44週制」を導入。スタッフの働き方を変えながら、会員の満足度をさらに高めることに挑戦しています。その取り組み内容や効果について、総務人事部 課長として施設運営に携わる畠中 聡氏に伺いました。
INDEX
PROFILE
畠中 聡 株式会社周南スイミングクラブ 総務人事部 課長
山口県にある大手総合化学工業メーカーである株式会社トクヤマの関連会社である周南スイミングクラブに、運営担当者として2006年に入社。少子化が進む現代においても安定した運営を確立するため、数々の改革を実行し、スイミングクラブの経営を支える。2025年からは、44週制の導入という新しい取り組みをスタートさせた。
1. 地域貢献と水泳教育の両立を目指して創立された周南スイミングクラブ
—— 周南スイミングクラブは、1978年の創業以来、地域に根差した運営を続けています。設立の経緯を教えてください。
周南スイミングクラブは、株式会社トクヤマ(以下、トクヤマ)の60周年記念事業として開設されました。トクヤマの事業であるセメントや化学製品、半導体関連材料を製造する中で発生する水・電気・蒸気を有効活用していることが特徴です。1992年には、少子高齢化を見据え、大人専用の総合クラブ「アクス周南」も開業しています。あわせて、小学生向けには民間学童保育「アクスキッズ」や、運動能力の向上を目的とした学童向け運動プログラムも提供しています。
—— 畠中さんが入社されたのはいつですか?
以前はトクヤマの関連会社で働いていましたが、声をかけられて約20年前に入社し、以降は施設運営に携わっています。
—— これまでに運営に最も影響を与えた出来事は何でしょうか?
やはり新型コロナウイルスの感染拡大です。成人会員数はコロナ禍で大幅に減少しました。現在も回復は鈍く、コロナ前の約8割です。子どもの会員は戻りが早かったですが、周南市の0〜14歳人口は1995年から2020年で約1万人、4割減っており、少子化の影響は避けられません(1995年・2020年の総務省「国勢調査」より)。

2. 顧客満足度向上と働き方改革を両立する44週制の導入
—— そのような中で、2025年から48週制を44週制に変更したそうですね。
大きくは次の2つの目的のために実施しました。
①顧客満足度向上につながるようなイベントや研修の時間を確保するため
②今いるスタッフの有給休暇取得率向上を含めたワークライフバランスの改善、およびそれによる人材確保のため
調査の結果、実際に48週すべて通っている会員は少なく、多くが44週程度しか通っていないことがわかったんです。そこで、44週制に合わせ、カリキュラムを見直しました。
—— どのような形で週数を削減したのでしょうか?
単純に1ヶ月休校にしてしまうと、その月の会費収入が0になってしまうので、お盆や年末年始、GWの休暇を長めに設定し、1ヶ月の営業週が4週の月と3週の月があるように調整する形で削減しました。48週制の時は、休校にした分の振替が翌週に集中し、休んだ意味がないような状況でしたが、今はスタッフが心身ともにしっかり休める環境が整いました。
—— 会費据え置きで週数を減らすと、会員から不満が出ませんでしたか?
実質的な値上げとなるため懸念はありましたが、次の3つの工夫でメリットを感じていただけるようにしました。
- 振替制度の緩和:振替回数を「月1回から2回」に増やし、有効期限も「翌月末から翌々月まで」に延長することで、通いやすさを向上させました。
- メダル授与制度の拡充:これまでは最上位級への進級者にのみ、トロフィーをプレゼントしていましたが、多くの子どもにとって目標になりにくい状況でした。そこで、身近な級でも進級時にメダルなどを贈呈し、達成感を得られる仕組みにしました。
- イベントの充実:進級テスト前の無料レッスンやアクアスロンイベントなど、新たな楽しみを提供しました。特にアクアスロンでは、水泳が苦手でも走るのが得意な子が活躍するなど、子どもたちの新しい一面を発見する良い機会となりました。
—— 44週制に対する社内の反応はいかがでしたか。
パートスタッフからは収入減を心配する声がありましたが、学校水泳の指導や監視業務などをお願いして労働時間を確保しました。実は、社員だけでは残業が必要なほど忙しかったので、社員、パートスタッフ双方にとってメリットのある改革となりました。

3. 子どもたちの心理に寄り添い、保護者も満足する運営を目指す
—— これからの運営について、新規会員の獲得も大切かと思いますが、より重きを置くのは、今いる会員に長く続けてもらうことでしょうか。
そうです。継続月数を伸ばすためには、子どもたちの目標と気持ちを正しく理解し、それに合ったサービスを提供することが不可欠です。つい「自分が子どもだった時の感覚」で考えてしまいがちですが、当時と今の子どもたちを取り巻く環境はまったく違います。今後は、スタッフが指導スキルだけでなく、子どもたちの心理についても学べる機会を設ける必要があると考えています。
—— 保護者向けの取り組みも考えていますか?
はい。保護者の満足度向上に向けたイベントも企画していきたいです。44週制への変更で生まれた時間を使い、多様なコンテンツで、新しい価値を届けていきたいですね。