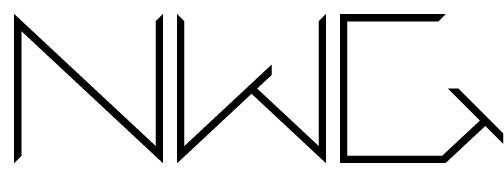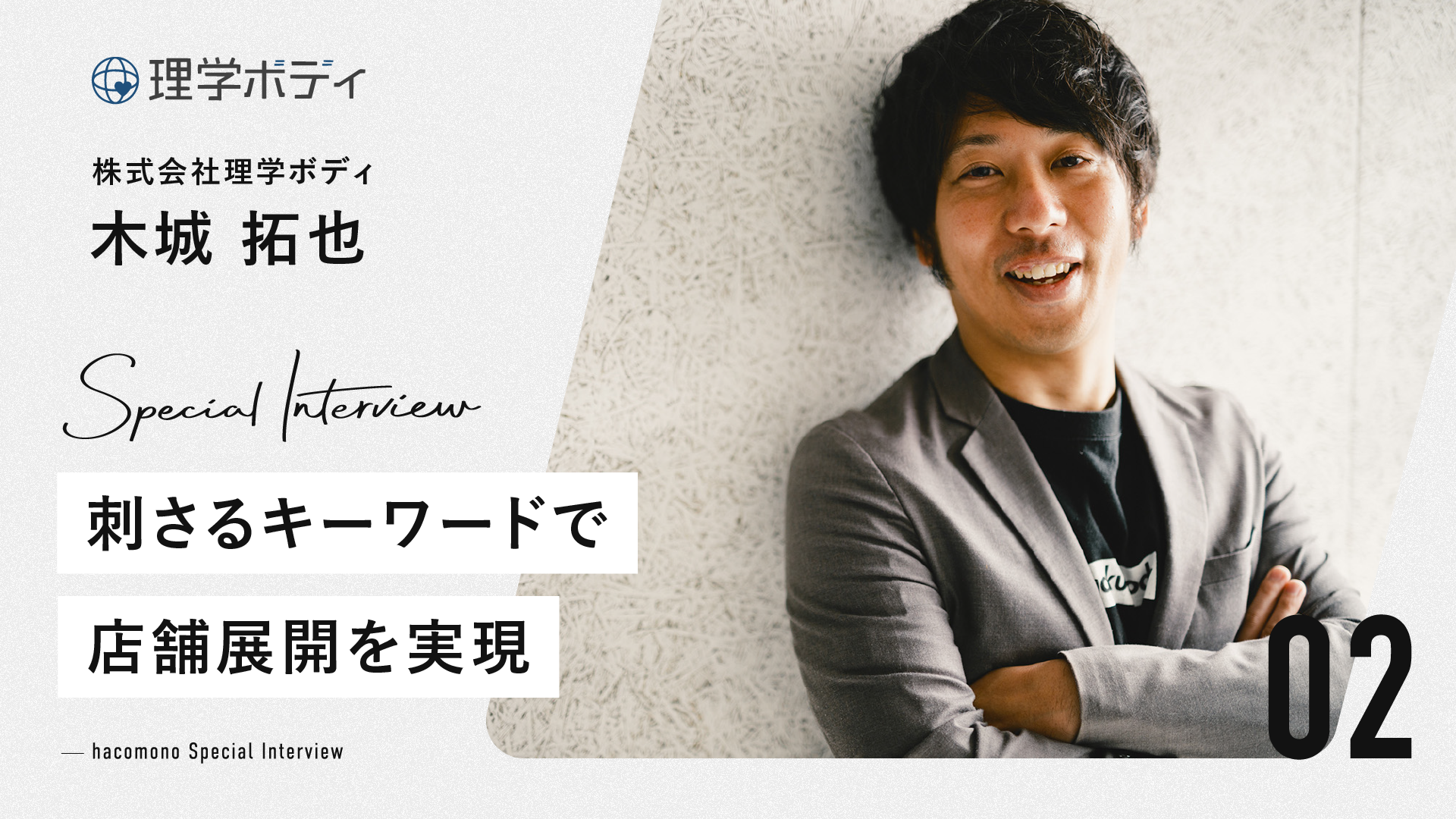倒産の危機に直面した沖縄スイミングスクールは、どのようにして経営を立て直したのか?二代目社長の大湾 朝仁氏は、「基本の徹底」「デジタル化」「人事評価制度」という3つの改革を断行し、見事に再建を果たしました。厳しい時代を乗り越えた革新的な経営戦略と、スタッフ・顧客双方の満足度を高めた秘訣について、大湾社長にお聞きしました。
INDEX
PROFILE
大湾 朝仁 株式会社沖縄スイミングスクール 代表取締役社長
大学卒業後、飲食業界でキャリアを積む。その後、父である大湾 朝史氏(現会長)が立ち上げた沖縄スイミングスクールの経営危機を機に故郷へ戻り、再建に尽力。スイミング業界の常識に捉われない数々の改革を次々と実行し、同社を立て直した。2020年、朝史氏の跡を継ぎ、代表に就任。現在は、より良い運営を目指し、さらなる改革に取り組んでいる。
1. 「オリンピック選手を育てたい」父親が始めたスイミングスクール
—— 沖縄スイミングスクールは、1982年にお父さまが創業されたそうですね。
父は中学時代に水泳選手として活躍し、1965年には全国中学校選抜水泳競技大会のバタフライ200mで日本一になりました。その後、オリンピックを目指すも夢が叶わず、「後輩たちに夢を託したい」という想いから、沖縄スイミングスクールを立ち上げました。当初はホテルのプールを借りてレッスンをしていましたが、創業から1年後には民間企業が運営する県内初の屋内温水プールを建設しました。
—— 創業当初の反応はいかがでしたか?
沖縄は海に囲まれていますが、当時は水泳を教える教室がほとんどなかったので、泳げない人が多かったんです。そのため、オープン直後から予想をはるかに上回る入会者が殺到しました。現在の2〜3倍にあたる2,000〜3,000名もの方が集まったほどです。その反響もあり、事業として成り立つと確信し、そこから2年スパンで施設を増やしていきました。
—— 総合クラブの「ガルフスポーツクラブ」もスタートし、現在はスイミングスクール6校、総合クラブ3施設を展開されています。大湾さんは2020年に代表に就任されましたが、それまでの経緯を教えてください。
2000年代、「生活習慣病」や「メタボリックシンドローム」などの言葉が広まり、健康ブームが訪れました。当社でも2006年6月に県内最大規模の「ガルフスポーツクラブ牧港」をオープンしたのですが、土地や建物施設への過剰投資や開設当初に会員数が伸び悩んだことなどが原因で、経営を圧迫することになります。
一方、私は、幼少期からスイミングスクールに通っていましたが、中学からはチームスポーツに憧れてバスケットボールに転向しました。大学で上京し、卒業後は飲食業界で働いていましたが、ある時、会社が債務超過に陥っていることを知り、父から「沖縄に戻って手伝ってくれないか」と打診を受け、入社を決めました。
当時は、倒産危機にある会社として金融機関から厳しい監視下に置かれていました。新たな取り組みを行うには、その都度、金融機関の許可が必要です。倒産危機を脱し、2020年にその制限がようやく終わったタイミングで私が代表に就任しました。

大湾 朝仁氏
2. 倒産危機を救った3つの改革:基本の徹底、デジタル化、公平な人事評価
—— 会社の再建に向けて、具体的にどのようなことに取り組まれたのでしょうか。
一発逆転の方法などありません。まずは、次の3点に注力しました。
1. 基本動作の徹底と接客の標準化
電話対応: 3コール以内の応答、笑顔が伝わる明るい声の出し方を徹底しました。
お客さま対応: ご要望に対して「できません」と即答するのではなく、「社内ルールに基づき検討します」など、お客さまに寄り添った対応を心がけました。
送迎バス: クラブの看板を背負っているという意識を持ち、安全運転と他車への配慮を徹底しました。
2. ナレッジ共有によるサービス品質の向上
良い取り組みが各店舗内で埋もれてしまわないよう、全店舗で共有する仕組みを整えました。たとえば、清掃方法や美化への取り組みは、文字だけでなく画像も使ってわかりやすく共有するため「Evernote」を導入しました。これにより、全店舗のサービス品質を底上げすることができました。
3. 公平な人事評価制度の導入
それまでは上司の肌感覚に頼っていた評価制度を、外部の専門チームの協力を得て見直しました。目標設定と評価基準を明確にすることで、スタッフは何を頑張れば評価されるのかがわかりやすくなりました。その結果、未納者への連絡が徹底され、未納件数が大幅に減るといった効果も現れました。
並行して、ホームページやSNSを積極的に活用しました。経営が厳しい時こそ広告宣伝を止めず、会社の強みである「スタッフの人柄の良さ」や「指導力」を丁寧に発信し続けることで、時間をかけて集客につなげていきました。

3. トップダウンから脱却し時代に合わせた経営スタイルへ。地域に貢献する多角化経営を目指す
—— 様々な改革を実行されてきましたが、長年業界にいたスタッフや会長から、改革への反発はありませんでしたか?
ありました。スタッフや、父である会長とは「業界の常識」について何度も衝突しました。しかし、私は外部から来たからこそ、お客さまと同じ目線で物事を見られると確信していたので、その想いを粘り強く伝え、最終的には「やってみなさい」と任せてもらうことができました。
また、それまでのトップダウンな社風から、現場スタッフの声を聞き、それを経営に活かすボトムアップな経営にも切り替えました。納得感を持って働いてもらうためには、スタッフの声に耳を傾けることが不可欠だと考えたからです。また、会員管理システムやホームページの刷新、送迎バスのスタッフとスムーズに連携できるIP無線の導入など、私が進めてきたデジタル化は、今や当社の強みになりつつあります。
—— 時代に合わせた経営に大きく変えていったのですね。今後はどのようなことに取り組もうと考えていますか?
現在はスイミングとフィットネスの2事業体制ですが、コロナ禍で事業の脆弱性が露呈したため、今後はM&Aも含めて複数の事業の柱を構築していきたいと考えています。沖縄県内では後継者不足で廃業する施設も多いため、シナジーがなくても地域貢献につながるのであれば、積極的に検討していきたいです。
また、3年前に新設した事業戦略部を中心に、既存事業の強化も進めています。地方自治体とのPFI事業や、学校の水泳指導の受託事業などもその一環です。選手強化にも引き続き力を入れていきます。