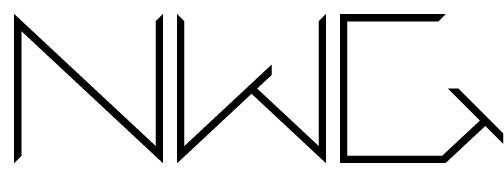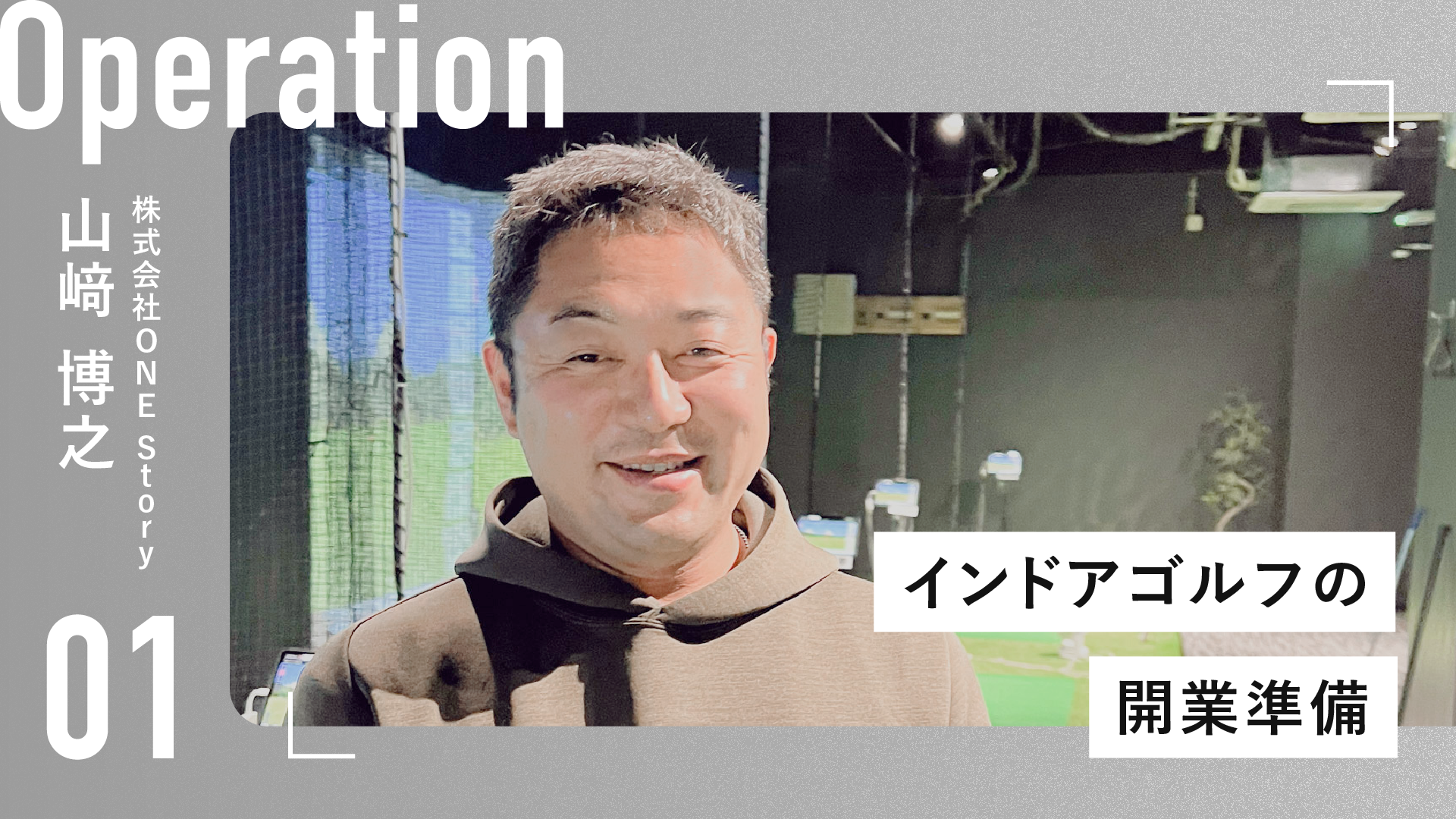子ども向けスクールは単にスキルを教えるだけでなく、子どもたち自身が社会でたくましく生きていくための「生きる力」を育む役割も担っています。神奈川県藤沢市で30年以上ダンススクールの運営に携わる、「Studio HANA!」代表の深澤 きよ美氏もその想いのもと、ダンスを通した“人間共育”に力を入れています。同氏に、スクールの運営において大切にしていることや取り組んでいることについてお聞きしました。
INDEX
PROFILE
深澤 きよ美 (HANA) 株式会社HANAエンタープライズ 代表取締役社長
1983年、劇団四季アクターズに合格。1985年にはタップダンサー中川一郎氏にスカウトされ芸能界入りを果たす。同年、渡辺プロダクション マイピストプランニング チーフインストラクターに就任。その後はタレント、ダンサー、インストラクターとして多岐にわたり活動する。1988年に渡米し、総合エンターテイナー育成およびアーティスト・プロダンサー育成指導を学び、帰国後は、その知識と経験をもとに独自開発のプログラムで指導を開始。2002年には「Studio HANA!」を開設する。2005年からはストリートダンス世界最高峰の大会「WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP」に挑戦し続け、金メダルを含む数々のメダルを獲得。その指導力と実績を世界に示している。
1. 娘を楽しませるためにママ友とダンスサークルを立ち上げ
—— ダンススクールを立ち上げた経緯を教えてください。
娘が幼稚園に通っていたころ、8ヶ月の息子が100万人に1人と言われる難病(重症複合型免疫不全症候群)にかかり、子ども医療センターに入院(骨髄移植)をすることになりました。私が息子に付き添っている間、娘は、病院内にある3畳ほどの場所で隔離待機です。寂しい思いをしていることを感じたママ友たちが、ある日「娘さんのために、週に1回でも、母親や友だちと遊べる機会を作ってみては」と提案してくれたんです。そこで、ダンスが好きな娘のために、娘の友だち5人、ママ友5人の10人で34年前にダンスサークルを立ち上げ、週に1回、ダンスの練習を行うことにしました。このサークルが「Studio HANA!」の前身です。
—— わずか10人のダンスサークルから始まったのですね。そこからどのようにして成長していったのでしょうか。
練習しているうちに、子どもたちのいきいきとした表情を多くの方に見てもらいたくなって、地域のお祭りでダンスを披露させていただきました。当時、子どものHIPHOPダンスサークルは1つもなかったため共感いただき、娘と同じ幼稚園に通う保護者を中心に「自分の子どもにも習わせたい」という要望が殺到して、1年後には一気に150名まで生徒が増えました。私は病院通いが続いていましたから、先生になっていただける方を急遽探し、私がレッスンをしてから病院に行ったり、ほかの先生にレッスンをお任せしたりしました。
—— その後の運営は順調でしたか。
指導をお任せしてしばらくすると、指導への熱意が違うのか、多くの生徒から「HANA先生(深澤氏のスクールでの通称)がいい」という声が寄せられるようになって。やはり自分でやらなければと取り組んでいたら、気づけば1週間で19レッスンも担当していました。すると、今度は私が倒れてしまったんです。病院で検査を受けたら胃がんであることが判明し、余命3ヶ月と宣告されました。しかし、放射線や抗がん剤などはせずに、しっかりと人生と生活を見直すチャンスを神様にいただいたと考え、また「なぜそこまで放っておいたのか?」と自分に問いただして、そこから色々なことをたくさん学びました。遺伝子レベルの食育マイスターのライセンスやブレイン(脳)マスターのライセンスを取得したりと、現在の育成指導に大きな変革を起こす、根底を見直すきっかけとなりました。考えてみればそれが必然であったことに気付かされました。
また、胃がんと闘うなかで改めて自分のやりたいこと、やらなければならないミッションを見直し、「子どもたちの教育にこそ力を入れるべきだ」という想いを強くしました。今後のダンススクールの在り方として「店舗のフランチャイズ化でダンサーを大量生産するのではなく、一人ひとりオリジナリティのあるダンサー職人作りに取り組もう」と決意したのもこのころです。

ストリートダンス世界最高峰の大会「WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP」で受賞した数々のトロフィー
2. ダンススクールで“人間共育”、「Studio HANA!」の3つの育成方針とは
—— 「Studio HANA!」の指導の特徴について教えてください。
大きく3つあります。1つ目は、ダンスをツールとして、“人間共育”を行うスタジオであることです。スタジオでのレッスンを通して、「自立」と「自律」できる子どもを育てたいと考えています。困った時にすぐに親に頼るのでなく、課題や解決策の発見まで、自ら考えて行動していける子どもを育てたいと考えています。そうすることで、例え何か落ち込むことがあっても、這い上がる力も身に付きます。そのように雑草魂のある子どもたちを育てることが、強いては世界に台頭できる日本を育てることにもつながっていくはずです。
—— “共育”のために、具体的にどんな取り組みをされているのでしょうか。
長年続けていることの1つに、お金の価値を感じてもらう取り組みがあります。20年ほど前、世界大会へ出場し始めた時に、子どもたちに自分たちのパフォーマンスの価値を知ってもらおうと、「投げ銭」ストリートダンスを導入したことがきっかけです。最高で1万円という方もいましたが、ほとんどの方は100円や多くて1,000円。世界大会に参加するための当時30万円という費用を、お父さん・お母さんがどれほど大変な思いで用意しているか。その「ありがたみ」と「感謝の気持ち」を感じて欲しいという気持ちもありました。
現在も、世界大会への活動資金を集めるため、子どもたち自ら支援を呼びかける活動も行っています。月1,000円のお小遣いの子が10円を寄付するのと、30万円をもつ大人が1,000円を寄付するのとでは、その重みが違います。これらの活動を通して、子どもたちに真のお金の価値や意味、そして応援してくれる方々への感謝の心を育んでいます。
—— お金を稼ぐ大変さやありがたみを感じることで、ダンスへの熱意も間違いなく変わっていくと思います。続く、2つ目は何でしょうか。
オリジナリティのあるダンサーの輩出を目指し、幅広いカリキュラムを取り入れたオリジナルプログラムを提供していることです。特定のスキルのみを磨いていくスタイルであれば早く成長できると思いますが、その土台に亀裂が入ったらすべて崩れてしまいます。その点、ジャズやバレエ、ブレイクダンスなど、幅広いスキルを習得していれば、表現の幅が広がることはもちろん、再び立ち上がることも容易になり、オリジナル性も生まれてきます。
—— 1つのスキルを突き詰める職人のようなダンサーを育成するのではなく、一人ひとりのオリジナリティを伸ばす指導を重視されているのですね。では、最後の3つ目を教えてください。
私が大病をしたこともあり、食育にも力を入れていることです。添加物だらけの食事をしていて体力が続くわけがありません。外で提供されたものはありがたくいただきつつも、自分で選ぶ時はできるだけ添加物の摂取を控え、体力温存、健康的な基準食(いも、まめ、青菜、海藻)を意識するよう指導しています。保護者にも「子どもが健康であることこそが一番の親孝行であるはず」と伝え、食生活に意識を配ってもらっています。
3. ダンス指導者の育成とα世代・Z世代との対話が課題
—— HANA先生の、子どもたちの育成に対する情熱、環境作りは本当に素晴らしいです。一方で、同じ情熱で指導できる方を探すのはなかなか難しいように思いますが、指導者の採用や育成面の課題はありますか。
私の考えをいかに発信し、同じ志の方を集めるかは、非常に難しいですね。だからどうしても、教え子や、教え子が「この人なら」と紹介してくれた指導者が中心になります。応募してくれる方もいますが、採用面接でこちらが「何か聞きたいことはありますか?」と聞いて、何も質問が出てこない方は採用しません。現場では、子どもたちからいろいろな質問が出ます。面接で反応できない方が、子どもたちの質問に反応できるとは思えないからです。子どもの質問に、例え回答がわからなくても「わからないから、一緒に考えよう」というような対応ができる方ならば、指導者に向いていると思います。
—— 30年以上ダンスの指導を行ってきて、昔と今で、違いを感じることはありますか。
今の若い世代は、昔と違い、情熱を表に出すことは「恥ずかしい」と感じるようですね。また、昭和世代の私たちとは価値観も違う。お給料は自分が生活できる分だけあればいいし、大会で一度メダルをもらえたら満足。情熱の火を灯すタイミングや、その火を燃やし続けることが、昔と違って難しくなったと感じます。
—— あらゆる場面でデジタル活用が進む時代にもなりましたが、貴スクールでも活用していますか。
当スクールでは、現在でも先生たちの業務日誌は手書きとしています。「もっと手軽なデジタルに変えましょう」と言われますが、文字として書くからこそ意識に強く残り、発する言葉も変わっていくと考えています。
一方で、コロナ禍ではいち早くオンラインレッスンを導入しましたし、生徒や保護者のためになると考えられる場面にはデジタルを活用しています。同じような考え方で、「売上を伸ばしたい」という理由だけで事業拡大はしません。まずは生徒や保護者を含めた、身近にいる人たちを幸せにすることを第一に考えて行動していきます。その結果、事業が拡大していくならば、理想的な成長フローといえますね。
—— 成長期の子どもたちを預かるダンススクールだからこそ、教育面でも力を入れているのがとても素晴らしいです。同じようなダンススクールがもっと増えて欲しいと心から感じました。本日はありがとうございました。
※Z世代:一般的に1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代
α世代:Z世代の次に位置し、おおよそ2010年代半ばから2020年代半ば頃に生まれた世代を指す