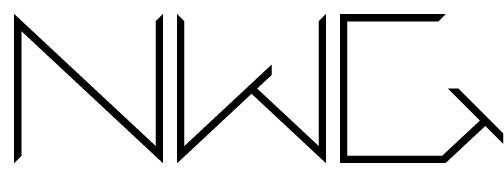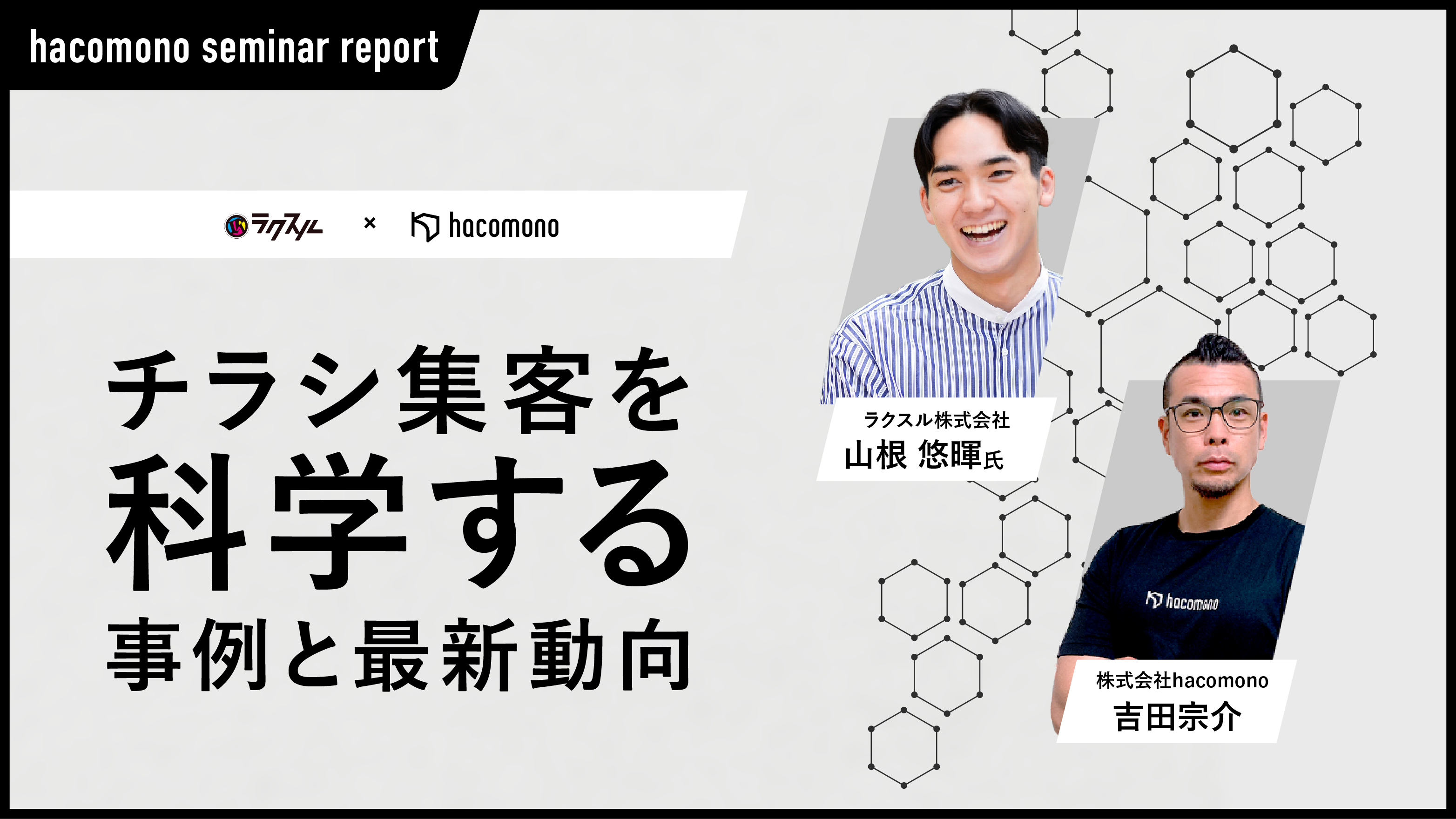【後編】この記事は2回に分けてお送りしています。
【前編】はこちらから
前職のアスリートマネジメント会社でも数多くのSNSショート動画を展開してきた田中 義朗氏。TikTokフォロワー数10.6万人を誇るバスケ選手のブレインとして、数々のショート動画戦略を仕掛けてきました。自身もインフルエンサーとして活動し、アスリート/スポーツチームへのSNSマーケティング支援を展開する株式会社ライズアスリートで顧問を務める田中氏に、フィットネス施設がとるべきショート動画のSNS戦略について具体的に教えていただきました。(※2023年11月インタビュー)
INDEX
PROFILE
田中 義朗
早稲田大学卒業。株式会社スポーニアで創業役員としてスポーツ×動画投稿アプリの開発に従事。 その後アスリートのマネージメント会社を創業し、アスリート・プロスポーツチーム・フィットネスジムなどを対象に、SNSを活用したスポーツマーケティング事業を展開。現在は個人でインフルエンサーとして活動する傍ら、スポーツSNSマーケティング事業を展開する株式会社ライズアスリートの特別顧問として、アスリートのSNS活動の支援を行う。
1. フィットネス施設がとるべきSNS戦略
1-1. 投稿の“量”と“質”を追求
ショート動画に取り組む場合は、ショート動画の“量”と“質”を追求する必要があります。前記事でも述べましたが、スポーツ・フィットネス動画というのは、もともとコンテンツ力が高いため、ある程度は質を担保できますので、とにかく量を投下し続けることがより重要になります。視聴者に常に新鮮な動画を楽しんでもらえることが大事です。最低ラインとしては、1日1投稿は必要でしょう。それぐらいやらなければ効果を出すことが難しいため、もし「毎日なんて無理」ということであれば、そもそもショート動画にかける工数や予算をほかの広告に回した方が効果的かもしれません。
1時間のレッスンを撮影しておけば、必ず3〜4回は絵になるシーンがあるはずです。1回のレッスンで3〜4動画作れるので、10回分のレッスンを撮影しておけば、30動画、1ヶ月分のコンテンツは確保できます。
1-2. 店舗アカウントと個人アカウントの使い分け
アカウントは、2つの属性のものを作った方がいいです。1つは店舗アカウント。これは店舗の公式アカウントとして、属人性の低いものです。もう1つは、トレーナーさんや選手の個人アカウントで、パーソナリティを感じられるものです。
SNSでは、個人が発信することが受け入れられやすいため、個人アカウントの方が短期的に数字を上げられます。また、フィットネス施設など「人が指導する」特性を持つ場合、他店舗との差別化のために、トレーナーやインストラクターという「人」自体が一定の影響力を持つことが重要です。そのため、個人アカウントはきちんと企画と構成を考えて質の高い動画を作成することが求められます。
店舗アカウントは、インターネット広告だけでは伝わりづらい店舗での体験などを、可視化して紹介することができます。質を重視しなくても、1時間のレッスンの切り抜き動画でも問題ありません。
質を重視した個人アカウントでは短期間で一気に影響力を高め、店舗アカウントでは、量を投下してその店舗のことをあまねく理解してもらう。インフルエンサー育成と体験の可視化、この2軸での運用方法がもっとも有効です。
両軸で取り組むことが難しい場合は、店舗アカウントでとにかく量を追求して、レッスンの様子やTIPSといったあらゆるものを可視化していく方にコミットするといいでしょう。
細かいテクニックとしては、個人アカウントの動画は最初にTikTokで反応を見ます。TikTokで評価される動画は、総じてSNS上での評価が高い傾向があるため、TikTokで高評価だった動画をInstagramやYouTubeショート、LINE VOOMに投稿していきましょう。質よりも量を追求していく店舗アカウントの動画に関しては、TikTokではあまり伸びず、InstagramとYouTubeショートが伸びやすい傾向にあります。

1-3. 冒頭3秒が最重要!最後のCTAも忘れずに
ショート動画で重要なのは、視聴完了率、視聴維持率を高めることです。視聴者が最後まで動画を見続けるようにするためには、冒頭2秒にハイライトを持ってくることが重要です。技やスキルをスロー再生でリプレイするといった工夫で動画としてのコンテンツ力はあがりますし、視聴者が最後まで動画を視聴する確率も高くなります。
また、最後のCTA(コールトゥアクション:サイトの閲覧者にとってもらいたい行動)も必要です。例えば、「体験イベントに来てほしい」といった文言や、店舗やスクールの名前とリンクを最後に入れましょう。ショート動画でもCTAは機能するので、視聴者の行動を喚起する文言やリンクは必要です。
1-4. ショート動画は投稿量と視聴完了率
ショート動画の分析で押さえるべきポイントは、フォロワー数やいいねの数よりも、どれだけ量を出せたかと、視聴維持率と視聴完了率になります。視聴維持率は50%、視聴完了率は10%あれば合格と考えています。
あとは、ショート動画を活用したSNSマーケティングの話になってくるかと思いますが、LINEやメルマガといったナーチャリング用メディアへの登録率も重要です。一概には言えませんが、アカウント全体のフォロワー数/登録数に対する登録率としては10~20%(Cf.1,000フォロワーのアカウントから生み出せる登録数は100人)が水準で、目標値は20〜30%くらいでしょうか。
1-5. 目指すべきは体験価値を最大化させる現地コンテンツへの集客
SNSで影響力を持ち、発信力を高めることは、言わば現地コンテンツにつなげるための第1フェーズです。第2フェーズとして、必ず来店動機につながる現地コンテンツを作りましょう。ショート動画は言わば擬似体験ですから、次のステップとして実際に店舗で体験してもらうことが必要です。
現地コンテンツは、1回で最大限の体験価値を提供できる独自のものにしましょう。長期間続けることが前提となっている通常のレッスンだと、インパクトが弱いためコンテンツの質として低いものとなってしまいます。1回で「このレッスンを続けていれば、最終的にこういうことができるようになる」という1年分の体験を疑似体験させるぐらいのものが理想です。アスリートを呼んで実演会をやったりと、何かインパクトのある特別なイベントを設定しましょう。

2. フィットネス、スポーツクラブがSNS領域で目指すべきカスタマージャーニーマップ
ショート動画を活用して認知度を高め、LINEやメルマガを通じて理解を深める。その後、より充実したコンテンツとしてYouTubeの長尺動画などを提供し、より魅力を感じてもらいます。最終的には、現地で最高の体験価値を味わってもらい、入会や購入につなげる。これが、フィットネス、スポーツクラブのSNS戦略として設定すべき最適なカスタマージャーニーマップだと考えます。SNSのショート動画を活用して、ユーザーや顧客との関係を強化し、店舗の魅力を広く発信することで、興味関心や顧客満足度を高めることに繋がります。店舗の価値を向上させるためにも、最適なコンテンツを継続して配信していけるように取り組んでいくことが重要です。