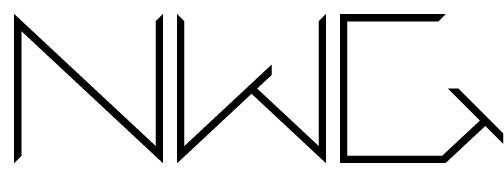加速する少子高齢化によって、フィットネス業界も他の業界と同様に人材不足に頭を悩ませる状況が続いています。あわせて、人材教育や人材流出についても、課題だと感じている経営者の方は多いと推察されます。
そこで今回は、フィットネスクラブの人材に関する課題感、インストラクターやトレーナーの流出の防ぎ方、人材育成の方法、取得を推進すべき資格などについて解説します。
INDEX
1. フィットネスクラブの人材に関する課題とは?
フィットネスクラブが直面している大きな課題は、インストラクターやトレーナーの人材流出と育成です。
少子高齢化の影響で、若いインストラクターやトレーナーを採用するのは年々難しくなっています。加えて、採用したとしても、すぐに辞めてしまうことが多いのが現状です。
主な退職理由は「評価制度が明確でないこと」「給与が十分でないこと」「勤務時間が長すぎること」「フィットネスクラブの運営に必要な知識や技術を体系的に教えるシステムがないこと」などです。
くわしく見ていきましょう。
1-1. 評価制度が確立されていない
インストラクターやトレーナーを適切に評価する評価制度が整っているフィットネスクラブは稀です。評価は昇給にも影響するため、努力して集客したり、質のいいレッスンを提供して継続率を上げたとしても、評価されず、昇給しないといった状態になると、退職しやすくなります。
独立したり、条件のいい店舗に移った方が得だと思われるためです。
1-2. スタッフのマネジメント意識の欠落による業務圧迫
スタッフの中には、限られた時間で効率よく業務をこなそうとしない人材がいます。そのしわ寄せがインストラクターやトレーナーにおよび、レッスン以外の時間も受付や事務の対応をしなければならず、結果的に過労働になって辞めてしまうケースも見受けられます。
1-3. マネジメント層が人材教育に時間を割けない
店長や支店長、支配人などのマネジメント層の業務には、インストラクターやトレーニング指導のほか、各種イベント企画、集客施策の実行なども含まれます。予算が達成できないとマネジメント層自身の評価が下がるため、集客や売上を上げるための施策に注力され、インストラクターやトレーナーへの教育が後回しになりがちです。
1-4. 携わる業務が多岐にわたる
インストラクターやトレーナーが現場で求められる業務は多岐にわたります。レッスンやお客さまとのコミュニケーション、清掃、受付、会計業務などに時間が取られがちで、トレーニング知識や栄養学、カウンセリング方法など学ぼうにも、その時間がありません。
2. フィットネスクラブにおけるインストラクターやトレーナーの流出を防ぐポイント
フィットネスクラブにおいて、インストラクターやトレーナーに長期間在籍してもらうためのポイントを解説します。
2-1. 従業員満足度調査の実施
インストラクターやトレーナーの意見を収集し、職場環境や給与などに関する改善点を把握するための調査を行います。インストラクターやトレーナーのニーズや不満に思っているポイントを理解し、待遇や業務内容、勤務時間などの改善に活かすことができます。
2-2. 360度評価制度の実施
店長や支店長、支配人などのマネジメント層や同僚、スタッフからのフィードバックを集め、総合的な評価を行う制度です。インストラクターやトレーナー自身も、評価に際して、自己評価や自己分析をすることになるので、より多面的かつ公平な評価ができます。
2-3. 実際に内部の改善を進める
従業員満足度調査の結果や評価制度のフィードバックで出てきた問題点に対して、改善策を実行することで、人材流出を防ぐことができます。店長や支店長、支配人などのマネジメント層が自ら率先して行うことで、インストラクターやトレーナーからの店舗への信頼度や心理的安全性が向上し、離職率の抑制にいい影響が生まれます。

3. フィットネスクラブにおけるインストラクターやトレーナーの育成ポイント
インストラクターやトレーナーを育成する際の具体的なポイントについて、解説します。
3-1. 基本的なトレーニング方法の育成
マシンはもちろん、フリーウェイトやダンベルといった基本的な器具の扱い方やトレーニング方法、お客さまの熟練度にあわせたレッスンやプログラムの立て方を教育します。
3-2. 栄養学に関する育成
トレーニングだけでは体は変わりません。体づくりの基礎となる栄養学の学習も重要です。トレーニングメニューに加えて、食事指導のサービスの提供にも繋げることができるため、ぜひ教育しましょう。
3-3. 機能解剖学や運動生理学などの基礎知識の育成
安全性を確保しつつトレーニング効果を最大化するためには、機能解剖学や運動生理学を学ぶことが重要です。知識のあるトレーナーは、お客さまにあわせた適切なトレーニングを提供できるため、高い評価や信頼を得られます。継続率の向上にもいい影響があるため、教育するとよいでしょう。
3-4. コミュニケーション能力の育成
インストラクターやトレーナーをやる上で、一番重要な能力と言っても過言ではありません。どんなに高いスキルや専門性があっても、コミュニケーションが円滑に取れなければ、お客さまは継続してサービスを利用してくれません。お客さまはもちろんのこと、一緒に働く店舗のメンバーのニーズも理解し、相手のモチベーションを高めながら、信頼関係を築けるようにしましょう。雰囲気のいい店舗作りを行う際にも、必須の能力です。
3-5. 自身の業務やお客さまに対するマネジメント力の育成
自身の各種業務のスケジューリングやお客さまの目標達成のためのレッスン・プログラムの進捗確認など、インストラクターやトレーナーには、マネジメント力が求められます。マネジメントのでき具合がお客さまや一緒に店舗で働くメンバーからの信頼度に直結するため、非常に重要な能力です。研修やOJTを行うなどして、教育するとよいでしょう。
3-6. コーチング力の育成
お客さまや一緒に店舗で働くメンバーが目標を達成できるように、励まし、時にはサポートしてゴールまで導くコーチング力も求められます。こちらも信頼度に直結するため、しっかりとした研修やOJTを行うと効果的です。
4. フィットネスクラブにおけるインストラクターやトレーナーが取るべき資格
インストラクターやトレーナーは資格を取得することで、その分野における専門性やスキルを証明することができます。
ここではインストラクターやトレーナーに関する代表的な資格を紹介します。今後のキャリアを考えるうえで重要な要素になりますので、ぜひ参考にしてください。
4-1. JSPO(公益財団法人 日本スポーツ協会)認定 「スポーツ指導者資格」
エアロビクス、ヨガ、トレーニングなど、多彩な分野の資格があります。スキルに合わせて資格を取得することができ、キャリアアップに役立ちます。
4-2. NSCA(全米ストレングス&コンディショニング協会)認定資格「CSCS」 「NSCA-CPT」
フィットネス業界では最も歴史のある資格です。科学的根拠に基づいたトレーニング、栄養、生理学が学べ、それに基づいたプログラムの作成を重視しています。
4-3. NESTA(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会) 「NESTA PFT認定」
トレーニングの他に心理学やビジネスも学べます。また、オンラインで学習できるため、自分のペースで学習できます。
4-4. 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 「健康運動指導士」「健康運動実践指導者」
日本スポーツ協会が認定しているため、公的信頼性が高いのが特徴です。フィットネス業界での就職に役立てられます。
4-5. 一般社団法人 日本フィットネス産業協会 「フィットネスクラブ・マネジメント技能検定」
フィットネスクラブの経営やマネジメントの知識や技能を得られて、キャリアアップに役立ちます。
4-6. 公益財団法人 日本スポーツクラブ協会 「スポーツインストラクター」
運動生理学、栄養学、メンタルトレーニング、アスレティックトレーニング技術など、幅広い知識と技術を身につけられます。
4-7. 公益財団法人 日本スポーツ協会「アスレティックトレーナー」
アスリートのパフォーマンス向上やケガの予防・治療、リハビリテーションなどをサポートする専門家です。
4-8. 柔道整復師
身体の不調や痛みを改善するための施術を行う国家資格の専門家です。主に、手技療法、電気治療、運動療法、温熱療法を行います。
4-9. 理学療法士
リハビリテーションを行う国家資格の専門家です。運動療法や理学療法の技術を用いて、リハビリテーションを行います。

5. フィットネスクラブのインストラクターやトレーナーを育成する際の具体的な流れ
ここでは、フィットネスクラブのインストラクターやトレーナーを育成するための具体的な方法を解説します。
5-1. 人材育成の問題点を洗い出す
各インストラクターやトレーナーの性格や長所短所を把握し、適材適所を考えたうえで、教育機会を提供することが重要です。ポイントは、各課題や問題点を明確にしておくことです。
5-2. ツールを導入して人材育成の施策へ繋げる
各課題や問題点を明確にしたら、基準のしっかりしたツールを導入してください。ここでは、以下3つを紹介します。
・職業能力評価シート
職務適性やスキルレベル、改善点を評価するためのツールで、本人のスキルや知識の不足点を特定し、フィードバックを行うことで改善に導きます。評価対象者のキャリアアップにも役立てることができます。
詳しくは、厚生労働省の公式ページ「職業能力評価シートについて」をご覧ください。
・OJTコミュニケーションシート
実際の業務について、現場で指導する際に活用するツールです。業務内容や手順を説明することで、必要な知識やスキルを学ぶ基盤になります。OJTをする側は、受講者が正しく理解しているかどうかを確認でき、受講者側は、教わった業務内容や手順への疑問・不明点が質問しやすくなる効果があります。
詳しくは、厚生労働省の公式ページ「OJTコミュニケーションシート」をご覧ください。
・キャリアマップ
個人の能力開発に関する標準的な道筋を示したツールです。自己分析、目標設定、スキルマップの作成、行動計画の策定、定期的な振り返りを繰り返すことで、自分自身の能力や強み、将来の目標やキャリアパスを明確化できます。
詳しくは、厚生労働省の公式ページ「キャリアマップについて」をご覧ください。
5-3. 課題の発見と改善を繰り返す
マネジメント層とインストラクターやトレーナーが一丸となって、上記のツールをもとに現状を共有し、改善策を話し合って、PDCAを回していくことが大切です。それによって、人材育成が進んでいきます。
6. まとめ
インストラクターやトレーナーの人材流出は、フィットネスクラブにとって大きな問題です。少子化が進んでいる昨今、人材の流出を防ぎ、育成を進めるためには、評価制度を設けたり、労働環境を整えたり、技術的な資格取得のサポートやキャリアアップ支援をすることが、特に重要になってくるでしょう。